千里: -
ジュディ: -
千里の言い草についムッときた朋也は負けじと言い返した。
「別にミオが悪いわけじゃないだろ!? 八つ当たりはよしてくれよな! それを言うなら、ジュディがこんなとこに飛び込もうとしたのがいけないんだろうが!!」
朋也の反撃に千里は激昂した。朋也にすれば逆ギレもいいところだが。
「!! あんた、言うに事欠いてジュディの所為にするわけ!? 信じらんない!! もう……情けなくて涙出てきた」
一瞬彼女が本当に泣きだしそうに見えたので(中学時代に泣いていた場面に居合わせたことはあるが、彼自身が泣かせたわけじゃない)、全面的に自分の方に非があるとは思わなかったものの、仕方なく白旗を振る。
「あ~もう、謝るよ! ジュディの所為にしたのは俺が悪かった。この通り」
千里は膝を抱えて向こうを向いたまま押し黙っている。しょうがない、ほとぼりが冷めるのを待とう。まったく、非常事態だってのに何やってんだろな。
千里のことはほっといて台座のオブジェを調べにかかる。どっかにスイッチか何かついてないかな? まあ下手にいじってまた変なとこに飛ばされても困るけど……などと思いつつ、ぐるっと一周してみるが、結局出っ張りなり穴なり、いじると動きそうな部分は何も見当たらなかった。
文字らしきものも彫られていない。メーカーのロゴか製造年月日でも書かれていれば、これが地球製のものであると確認できたところだが。宝玉に触ってみるが、反応はない。
ジュディがそばにやってきて、一緒に胡散臭そうな目で見上げる。当人はそんなに機嫌を損ねてなさそうだ。まだ1人でいじけている千里をちらっと横目で見つつ、彼女の相棒に声をかける。
「なあ、こいつが怪しいと思うんだけど、どうかな?」
ジュディはしばらく周囲を嗅ぎまわったが、特に注意を引く臭いはしないようだ。朋也を振り仰いでぶるっと身震いする。その様子が「収穫なしだね」と首をすくめてるみたいで、何だかおかしかった。
続いて、彼女は台座の上から降りて周囲の草むらの検分を始めた。
「おおい、頼むからあんまり離れないでくれよ!」
木々の間にジュディの姿が隠れそうになったので、あわてて声をかける。千里がやっと身を起こしてこっちへやってきた。
「先にミオちゃんの所為にしたのは私だもんね。ごめん」
朋也の隣にやってきて小声で呟くと頭を下げる。それから少しはにかむように微笑んで見せた。
「こんな状況で私とジュディとあんたと3人しかいないんだもの……ケンカなんかしてる場合じゃないよね」
「ああ。もう気にしてないよ」
朋也もうなずき返す。まあわかってりゃ別にいいや。彼女の言うことはもっともだしな。
「ところで、朋也。あんた、お腹空いてるんじゃない?」
図星だった。晩飯をほとんど抜いて歩き詰めだったからなあ。なるべく考えないようにしていたし、そんな暇もなかったけど。腹の虫が先に返事をする前に朋也は答えた。
「よくわかったな」
「そのぐらい──」
言いかけて肩をすくめる。
「実は非常食の手持ちがあるんだけど、食べない?」
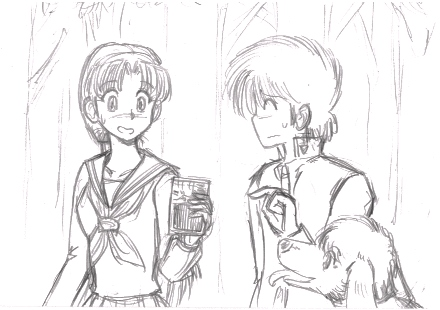 朋也は二つ返事でうなずき、手を差し出した。
朋也は二つ返事でうなずき、手を差し出した。
「じゃあ、はいこれ」
といって差し出したのはササミジャーキーだった……。まあ、別にこれでも腹の足しにはなるけど。
「あ、いけない! これはジュディのおやつだった。ジュディ、おいで! ちょっとおやつの時間にしよ♥」
台座の周りをウロウロしていたジュディは、おやつと聞いて跳んで戻ってきた。
「はい、朋也と私の分はこっち。これで仲直りだね」
取り出した袋に入っていたのはサンザシと干しイチジクの実だった。片手分受け取り、1つ口に運ぶ。しっとりとした甘味が口いっぱいに広がる。保存も利くし、確かに非常食にはうってつけだが……ゆっくり噛みしめつつ疑問を口にする。
「いつもこんなの懐に入れて持ち歩いてんのか? 学校まで?」
「いいじゃん、別に。小腹が空いたときとかに、ね」
「太るぞ」
ボソッと一言。
「いいのっ! 私は太らない体質なんだから」
そんなこと言ってると歳取ってから後悔するんだぜ……と忠告しようと思ったけど、取り上げられそうなのでやめにした。
3つずつ平らげて残りはしまうことにする。とても満腹とはいかなかったが、この先いつまともな食事にありつけるかわからないし。そういえば、ミオのやつはお腹空かせてないかなあ?
「そうだ! 俺も非常食を持ってきてたんだ」
ミオを見つけたら夜食にあげるつもりだった煮干のことを思い出す。彼女の分を取っておかなくちゃいけないので、朋也はお返しに千里とジュディに一掴み分ずつあげ、自分も口に放り込んだ。
ジュディは再び探索に取りかかった。朋也と千里も何か目ぼしいものはないか辺りを探ってみる。梢の向こうに隠れて見渡せないが、この世界の太陽も今まさに没しようとしているらしかった。朝が来てないのにもう一度夜を迎えるなんて、なんとも妙な気分だ。
西にあたる方角に明るい星が輝き始める。朋也は星にはそれほど詳しくなかったが、その星には確かに見覚えがあった。あれはひょっとしたら金星なんじゃないだろうか? だとすると、ここはやっぱり地球の上なのか??
〝ここは一体どこなのか?〟〝なぜ自分たちがこの世界に連れてこられたのか?〟という問題もさることながら、朋也たち3人にとって一番必要な情報は〝どうやったら元の世界へ帰れるのか?〟だ。そして、〝ミオはこの世界に来ているのか?〟──。もしそうなら、もちろん一緒に連れて帰らなきゃならない。
だが、今の彼には情報源が何もない。帰るどころか、当面の行動さえ手探りの状態だった。
間もなく異世界の夜が訪れる。見知らぬ森で何が現れるかもわからない。ジュディの存在はとても心強かったし、千里は十七歳の女の子としてはこれ以上望むべくもないほど頼りになった。それでも、彼らのもとにあるのはわずかばかりの非常食だけ、千里が持ってきていた懐中電灯はどこかで落としてしまったみたいだし、朋也の手には折りたたみ傘しかない……。心細い限りだった。
さっきからジュディが台座から少し離れた木の根元辺りを熱心に調べている。茂みに鼻を突っ込んでいたジュディは、不意に大声で「ワン、ワンッ!!」と千里たちを呼んだ。2人は彼女のもとへ急行する。
「!! それは!?」
草むらからのぞいていたのは、この世界へ来て唯一彼の知っている──それもよく見慣れたものに見えた。木々の下生えを掻き分け、一歩ずつ足取りを早めながらたどり着く。
「やっぱりミオの首輪だっ!!!」
朋也が郊外の専門店で見つけてきた、彼女の赤毛と対照を為す緑の首輪。小さな鈴のレプリカが付いているやつだ。首輪は鈴の位置の反対側、つまり首の後ろ辺りでぷっつり切れていた。もともと、万一枝などに引っかかったりしたときに首を絞めないようすぐに切れるというのでこれにしたのだが。
恐る恐る検分するが、特に異常な損傷や血糊などは着いていないようなので、ひとまず胸をなで下ろす。
「彼女も間違いなくこの世界にいるんだよな……」
じっと見つめてるうちに、朋也はなんだか目頭が熱くなってきた。ミオ……一刻も早く会って無事を確かめたい……。
同じように首輪に顔を近づけて見つめていた千里がこっちに視線を戻したので、あわてて鼻をこすり何でもないふりをする。彼は壊れ物を扱うようにそっとポケットにしまうと、2人を振り返った。
「ありがとう、ジュディ! お手柄だよ♪ 千里も……」
自慢げに尻尾を振っていたジュディが、そこで首を傾け、木々の間の一点を注視した。低い威嚇の唸り声を上げる。ミオの落し物を発見したときとは明らかに反応が違う。
ミオの手がかりを掴んだ喜びも束の間、一同の間にさっと緊張が走った。何かがいる──!?


