6 謎のネコ娘
太陽はすでに西にだいぶ傾いていた。アリ退治に続くハプニングの連続で、当初の予定どおり夜に入る前に森を抜けてビスタの街に到着するのはかなり難しい状況となっていた。千里とゲドの臭跡をジュディが確認しつつ、一行は北への道を急いだ。
朋也はずっと、ゲドとその一味が朋也たちの来訪を事前に知っていたのはなぜかを考えていた。ニンゲンがエデンに足を踏み入れると同時に警報を発する仕掛けでも持っていたんだろうか? そんなものがあったとしても、市井の住民が入手できる情報なのに、ゲートを設置した神獣と妖精たちが知らないことはないだろう。だとすれば、マーヤがたまたまゲートに訪れて自分たちを発見するというシチュエーション自体おかしいことになる……。
ちらりとマーヤのほうを見やる。ジュディを献身的に手当てしてくれた彼女が、少なくとも悪意をもって自分たちをだますなんて考えられない。だが……千里が誘拐された以上、きちんと確かめる必要があると朋也は思った。
「なあ、マーヤ。あのゲドってやつが、俺たちがエデンに来ていることを知ってたのはなぜだと思う?」
マーヤは困惑した顔で朋也を見つめた。言葉を探しているようだ。しばらく間を置いてからやっと口を開く。
「えぇ~っとぉ~……たぶん、う、占いか何かだと思うわぁ~♪ イヌ族の間で流行っているのよぉ、きっとぉ~……」
占いか。まあ、それなら説明は全部片付いてしまうが……。170年前に姿を消したはずの種族が再び迷い込んできたなんて珍事をピタリと言い当てられるとしたらたいしたもんだ。それにあいつは「確かな情報筋」と口にしていたし。
朋也には、ゲートを通じてニンゲンがやってくることは、誰かのスケジュールにあらかじめ組み入れられていたのではないかという印象が拭えなかった。いまのマーヤの説明で、彼の疑念は逆に深まった。彼女は思っていることがすぐ表に出るタイプなので、何かを隠しているのは嫌でもわかってしまう。
でも……これ以上追求するのはやめておこう。嘘を吐けない体質だというのは、朋也たちと接するときの打ち解けた表情も、ジュディのために流してくれた涙も、本物だということに他ならない。たとえ何らかの理由があって、本当のことを言ってないとしても、彼女を嫌うことは朋也にはできなかった。
話題を変えて、朋也がこれまでの出来事に関して疑問に思った点をいくつか尋ねてみることに。
まず1点は、ジュディの服装について。どうでもいい話ではあるが、素朴な疑問として、何で最初から着ていたんだろうと不思議でならなかった。まあ、変身したときに彼女がすっぽんぽんでなくて非常に助かったけど……。
マーヤにによれば、これもP.E.のなせる業だという。変身時にはP.E.の効果が極大化し、身に着けているわずかなものや、何もなければ手近なものから着衣が生成されるのだと。とすると、あれは全部首輪の延長なのかな? まあデザイン的にもそんな感じはするけど。
剣について訊くと、種族にはそれぞれ得意とする装備・アイテムがあり、例えばネコ族は爪、妖精族は弓で、イヌ族の場合剣なんだそうだ。これも変身時に調達されるらしい。ネコが爪なのは納得できるとしても、イヌが剣というのは変な気がするが、成熟形態になると牙では闘いづらいのは納得できる──特に女性の場合は。
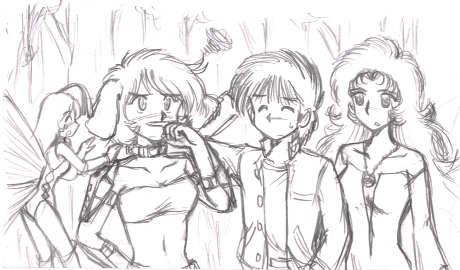 そう、2点目は成熟形態の男性と女性の違いについて。なんであんなに違うんだろうか?
そう、2点目は成熟形態の男性と女性の違いについて。なんであんなに違うんだろうか?
「よくわかんないぃ。神獣様のセンスなんじゃないのぉー?」
屁理屈をこねれば、文明社会に果たす役割という点では女性のポストのほうが大きく、男性は前駆形態との差が少なくてもさほど問題はないということなのか。ただ、どの種族でも大体同様だという。
マーヤに言わせると、ヒト族の男性がむしろ女性一般に近いのだとか。理由と呼べるかどうかわからないが、守護神獣は通常両性がいるか、単独の場合中性的な存在なのだが、ヒト族では完全な女性型で1人だったらしい。「だった」というのは、今はもう彼女はいないという意味か……。
不意にジュディが立ち止まった。
「あれっ??」
空気中の匂いを嗅ぎながら周囲を見回す。
「どうしたんだ、ジュディ? 千里の匂いか?」
朋也は隣に並んで尋ねた。
「ううん、違うけど。この匂いには嗅ぎ覚えがあるような……」
しきりに首をひねる。記憶にあるというのは、元の世界でってことだよな。判断がつかないのは、よっぽどその匂いがよっぽどかすかな所為もあるのだろうが。
ジュディは少ししょげ返った様子でつぶやいた。
「なんか、この格好になってから鼻の調子が悪くなったみたいだ」

