「仕方ない……。マーヤ、行くぞ!!」
「ええ! SクラスだろうがSSクラスだろうが、負けやしないわよぉー!!」
朋也は矢の雨を、マーヤは全体魔法を彼女たちに浴びせかけた。が、エデンの最も高度な管理業務をこなすクラスSの幹部妖精は、いずれも齢500歳を越える精鋭中の精鋭だ。これまで相手にしてきた下っ端とは格が違う。効果的なダメージを与えることができないまま、2人は直ちに反撃を受けてしまった。何しろ彼女たちは、いくら経験を積んだといっても所詮Cクラスにすぎないマーヤを越える魔力を1人1人が備えていた。その彼女たちが一斉に強力な魔法を放ってくるのだ。マーヤはいったん体勢を切り替え、魔法防御と回復のスキルに専念する。
悪くしたもので、これまでの戦闘で朋也の矢は底をつきかけていた。P.E.による補充では間に合わない。矢が使えなくなると、妖精に対抗できるほどの魔力のない彼は為す術がなくなってしまう。イヌ族、ネコ族のスキルも多少は使えるが、今は装備を持ち合わせていない。明らかに分が悪かった。
と、マーヤの羽が金色の光を帯び始めた。BSEを相手にしたときと同じだ。
「あたし……妖精としてただひたすらエデンのために尽くすのがあたしたちの定めだって……ずっとそう思ってた……。朋也に出会うまで……。でも、あたしだって生きてるものぉ! 自分が生きてるってことを実感できるものぉ! 悲しんだり……苦しんだり……悩んだり……人を好きになることさえできるんだからぁーっ!!」
金色の輝きはついに彼女の羽全体に広がった。まぶしさのあまりマーヤの姿を直視できないほどだ。
「トリニティーッ!!!」
マーヤは自身の使える最大威力の3属性魔法を発動した。だが、いつものトリニティではない。むしろエデン最強の魔法であるジェネシスを彷彿とさせた。管理塔全体に3色の閃光が満ちあふれ、近くの計器類は次々にショートしていく。直撃を受けたSクラス妖精たちはバタバタとくずおれていった。
朋也は呆然として傍らの小さな妖精の女の子を見つめた。さすがに顔には疲労の色を滲ませ、喘ぐように息をしている。すごいや……。エリート級の相手をまとめて倒してしまうなんて、落ちこぼれどころじゃない。一体この子は何者なんだろう?
ただ1人、至近距離で強力な魔法を受けてもダメージをほとんど被ることなく平然と構えていたディーヴァが、感心したようにつぶやく。
「なるほど……。キマイラ様がお前を選んだわけがわかりましたよ。標準偏差からの逸脱──スキルのインフレーション特性──そうですね、キマイラ様? ですが、私は妖精長としてこの者に裁きを与えなくてはなりません。これはあなたが私に委譲された権限ですもの……。どうかお許しください。最終任務は私が継承いたしますから……」
ディーヴァは回復系スキルのセラピーを唱えた。
「な!?」
朋也たちの見ている前で、数十名のSクラス妖精たちが見る見る回復していく。数秒後には、彼女たちは全員戦闘開始時と完全に同じステータスを取り戻していた。
「そんなぁ~……」
さすがに2人もがっくりと肩を落とす。ディーヴァは回復能力に関してもまさしく超一流のエキスパートだった。これではいくら戦っても勝ち目はない。
そのときだった。室内に新たにピンク色の光が充満した。頭がくらっとしたかと思うと、朋也の目の前に黒い花畑が広がる。オレンジの空を黒い無数の蝶が舞っている。そのビジョンは一瞬で消えた。今のは一体何なんだ!? 幻?? まったく、次から次へと……。
周りを見ると、パニックに陥ったSクラスたちが悲鳴を上げて狂ったように塔内を飛び回っていた。ある者はコンソールの下でガタガタと震え、別の者は床の上でもだえながら転げ回っている。朋也が一瞬垣間見た幻影に惑わされているんだろうか? まともに戦える状態の者はもはや1人もいなかった。マーヤも、ディーヴァでさえ何が起こっているのか事態を理解できずに困惑の表情を浮かべている。
ピンクの光は朋也とマーヤの頭上に渦を巻きながら凝集し始めた。中に大きな羽を持った妖精の姿が浮かび上がる。妖精といっても、マーヤたちのような実体のない、文字通りの〝スピリット〟だ。彼女はあろうことにも、ディーヴァに向かって悪戯っぽくウインクしてみせた。
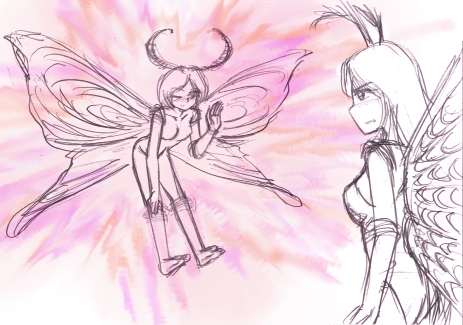 「お、お前はマリエル!?」
「お、お前はマリエル!?」
ディーヴァが驚愕の叫び声を上げた。たぶん、この100年間で初めてくらいだろう……。
マリエルだって!? それって、170年前に死んだはずのオルドロイ派のリーダーのことか?? 朋也たちが見ている前で、彼女の姿はすうっと消えていった。同時に、自分の身体が温かい光で満たされていくのを感じる。何だろう……まるで今までにない力を得たみたいな感じだ。
ディーヴァはやっと合点がいったというふうに口を開いた。
「そうでしたか……。あなた、わざと倒されたふりをして、自らのテロメアを制御していたのですね。オルドロイ派の者が、いざというときに霊力として自分を活用できるように」
「ああ、マリエル……。容を失ってまで、あたしたちのこと見護っていてくれたんですねぇ……」
マーヤは感謝の祈りを捧げるように手を合わせた。妖精の一族には守護鉱石と固有のスキルはあるが、神獣が存在しない。オルドロイの妖精長だったマリエルは、自らの身体を捨て、一族の守護者に代わる存在となる道を選んだのだった。
ディーヴァはステータス異常を回復するセラピーを重ねて部下たちに施したが、彼女と同等のSS級妖精マリエルの幻惑術の効果を打ち消すことはできなかった。あの子たちも、回復させられたりこてんぱんにのされたり、振り回されっぱなしで大変だな……。朋也はちょっぴり同情してしまった。
ディーヴァは再度2人に向き直り、笑みを浮かべた。確固とした自信にあふれた勝利の笑みだ。まだ奥の手があるってのか!?
「残念でしたね。お前たちにはあの者をもう一度この場に召喚する力はない。どのみち、私には通用しません。キマイラ様に選ばれたお前に、妖精一族の頂点に到達した者の真の力を見せてあげることにしますわ……」
ゆっくりと朋也に向かって近づいていく。
「#9109557。お前にはテンプテーションが使えて?」
「つ、使えるわよぉ、そのくらいぃ~」
明らかに強がりとわかる声だ……。
1世紀以上前に討ち滅ぼしたはずの仇敵マリエルと対面した一時を除き、そもそも感情があるのかさえ疑わしかった冷たい合理主義者の顔が、ドキッとするほど妖艶な表情に変わる。頬を紅潮させ、切なげなため息をかすかに漏らし、長い睫の下から潤んだ瞳で焦らすように見つめる。男性の心を鷲づかみにせずにはおかない完成された演技だった。こ、こいつ、俺を誘惑しようってのか!?
テンプテーション──それは、妖精族の特殊スキルで、敵の心を幻惑し、一時的に操ってしまう術だった。ディーヴァはその標的に朋也を選んだのだ。
「ちょ、ちょっとぉ~、あたしの朋也に何するのよぉ~っ!?」
マーヤが狼狽した声を上げる。
「お前たち並の下級妖精には、せいぜい低レベルのモンスターを数ターン懐柔するのが精一杯でしょう。けれど、SSクラスの私が行使すれば、相手の精神を完全に支配して意のままに操ることができるのよ。術を受けた者の寿命が尽きるまでね……」
身体のラインを強調するようにしなやかに肢体をくねらせながら、朋也の前まで来る。
「さあ、坊や……私の目を見て。そう……いい子ね。私だけを見るの。そうよ……私以外のことは何もかも忘れてしまいなさい……何もかも……」
「朋也ぁっ! 彼女の目を見ちゃ駄目ぇぇーっ!!」
マーヤが金切り声を上げる。

