その晩はゲドたちが寝泊りしていた公民館に一緒に泊めてもらい、翌朝朋也はクルルとともに彼女の実家であるラディッシュさん宅を訪れた。玄関の戸をたたくが、返事がない。
「おかしいなあ……もう畑に出てるのかな?」
まだ8時前なのに精が出るなあ。夕べ遅かったこともあるが、朋也なんてまだ半分頭が寝ている。
とりあえず村の共同菜園まで行っていると、はたして腰をかがめて秋野菜の収穫に勤しむ彼女の姿があった。
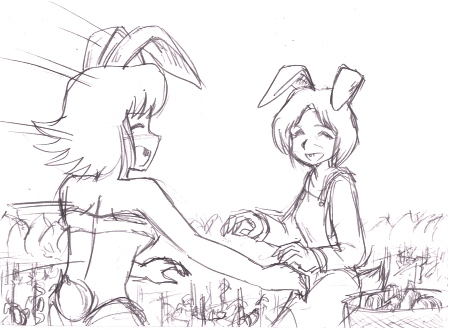 「おばさんっ!」
「おばさんっ!」
「!? クルルッ!!」
ラディッシュおばさんはナスビやらピーマンやらの入った籠を放り投げ、駆け寄るクルルを両腕を広げて迎えた。
「よかった……お前だけでも無事で。心配したんだよ?」
「うん……ごめんね、おばさん……」
抱き合う2人を前に、朋也もちょっぴりホロリとしてしまった。ラディッシュはそこで今朝の畑仕事を切り上げ、2人を連れて家に戻った。クルルと2人で朝ご飯をご馳走になる。彼女自身はもう済ませていたが。
食事がてら、お互いのその後について情報を交換し合う。ゲドたち3人によって、村の男衆たちを見舞った悲劇の報がユフラファに伝わると、村中が悲しみに包まれた。
ただ、あの3人組は献身的に働いてくれ、朋也の予想以上に役に立ってくれたらしい。実際はやっぱり時々……というか度々ドジを踏みはしたものの、おかげでウサギ族の女性たちも少しは明るさを取り戻してくれたようだ。村長夫人がビスタの妖精施設に使者を送って緊急支援を頼んだということだが、3人の方がむしろ頼りになるくらいだという。
一方、クルルの語った冒険譚は、おばさんには日常生活からかけ離れすぎて想像力が追い着かないようだ。目を見開き、首を左右に振りながら「おやまあ!」を連発するばかりだった。特に甦った神鳥フェニックスと戦ったり、彼女がゾンビになってしまったくだりなど、聞いただけで卒倒しかけたほどだ。クルルの身振り手振りを交えた臨場感たっぷりの説明のせいもあるかもしれないが。そんなに一部始終を細かく話さなくてもいいのに……。
「それにしてもおばさん、朝からホントに精が出るね?」
食後の一服にお茶をいただいて寛ぎながら、クルルが尋ねた。
「クレソンがいてくれりゃ苦労はしないけど……まあ、愚痴っても仕方ないからね」
「クレソン?」
尋ねる朋也に、クルルが小声でヒソヒソと囁く。
「おばさんの連れ合い。オルドロイで──」
ああ、そうか……。
「ところで、シエナから2人でわざわざ戻ってきたからには、理由があるんだろ? おばさんにできることがあれば何でも協力するから、言ってごらんよ?」
「うん……おばさん、クルルね、シエナの街でインレの村のこと耳にしたんだけど……」
「……そうかい、聞いちまったのかい」
ラディッシュは目を伏せるとため息を吐いた。
「クルルも今年で15なんだから、もう立派な大人だし……いつまでも伏せておくこともできないだろうから、教えるとするかね……」
テーブルの上で手を組み、2人の顔を見ながらポツポツと話し始める。
「クローバーはね、お前を逆に傷つけることはしたくないって、自分が本当の親じゃないことをお前に隠さなかったけど、言ってないこともあったんだ。お前が拾われたのは、インレへと通じる山道の入り口──大吹雪と雪崩と恐ろしいモンスターに襲われ、インレとの往来が不可能になっちまったその日だったのさ……」
クルルはゴクリと唾を飲み込みながら、育ての親の一人の話に真剣に耳を傾けた。
「……あたしらアナウサギ族はね、成熟形態の文明に参加を認められてからまだ歴史の浅い後発の種族なんだよ。エデンは人口の制約が厳しいし、新しく町や村を拓くのも簡単じゃない。あたしらの先代が、村の人口が増えたユフラファに次ぐ一族中心の街を築くことを申請したのは、規制が一段と厳しくなった170年前以降の話でね。やっと認可が下りたのは、大陸の北の外れの寒さも厳しい山奥だった。あたしたちゃ、とっても弱い種族だ……このエデンでさえ。それでも先代たちは、みんなで肩を寄せ合い、支え合いながら、頑張って新しい村を開拓したのさ。だけど、大雪にもモンスターにも太刀打ちできっこなかった。妖精たちには、雪に閉ざされた山奥の盆地に大がかりな救援隊を差し向ける余裕がなかったし、神獣様もモンスターを抑え、モノスフィアからの難民を救うのに手一杯だっていうしね。あたしらだけじゃ、連絡の途絶したインレに渡った同族たちを救う手立ては、残念ながらなかったんだ。あのとき、どんな運命の気まぐれでか、麓に置き去りにされた1人の女の赤ん坊を除いてはね……」
それを聞いたクルルがハッと息を呑む。ラディッシュはお茶を一口すすってから、さらに続けた。
「クルル……たとえお前がみなしごでも、みんなが力を貸してあげられる。そして、あたしらの望みどおりお前はしっかり者のやさしい子に育ってくれた……。でも、世の中には知らない方がいいこともある。忘れてしまった方がいいことも……。仮にインレがお前の故郷で、お前の両親がそこにいたとしても、あたしらの力じゃ会わせてやることも、生死を確かめることさえできないから──忘れることにしたのさ……村の存在自体を。すまなかったね、クルル。今までお前に黙ってて……」
クルルはゆっくりと顔を上げると、おばの手をとって微笑んだ。
「ううん。みんな、クルルのことを気遣ってくれたんだもの。おばさんにも、お母さんにも、村のみんなにも、今でもとっても感謝してるよ。でもね、クルルこれからインレへ行くつもりなんだ!」
ラディッシュは義理の娘の言葉を聞くと、驚いて目を見張った。
「およしよっ、そんな危ないこと!! 村の周りでさえモンスターが殖えてきてるんだし──」
「おばさん……クルル、自分がお父さん、お母さんに会いに行きたいわけじゃないの。みんなのために行きたいんだ! インレが今でも無事にあるのかどうか、自分の目で確かめにいきたい……そして、もしまだ仲間が元気に暮らしてるようだったら、ユフラファの再建のために力を貸してくれる人、みんなを支えてくれる人を、捜してきたいんだよっ! 大丈夫、朋也も一緒に来てくれるし、クルルだってちょっとはやれるんだから♪」
クルルが目を輝かせながらインレに向かう目的を話すのを、ラディッシュは黙って聞いていた。しばらく沈黙してから、あきらめたように微笑む。
「……クルル、お前はあたしらにゃとても及ばないほど強くなったんだね……。クローバーが今のお前の成長ぶりを見たらどんなに喜んだろう……。わかったよ、クルルの好きなようにおし。でも、無理だけはするんじゃないよ?」
「ありがとう、おばさん!」
「お兄さんも、クルルのことよろしく頼むわね?」
朋也に向かって頭を下げる。
「ええ、わかりました」
彼女は、クローバーさんや、クレソンさんや、ラディッシュさんや、村中のウサギたちに大切にされてきた、言ってみればユフラファの〝宝物〟だものな。俺が責任もって護ってやらなくちゃ──


