アニムスの塔の中には、すぐには入ることができなかった。取っ手が付いていなかったので自動ドアかと思ったが、前に立ってみても開かない。ジュディが体当たりしてもびくともしない。錠前外しの名人ミオがあちこち調べたが、そもそも鍵穴らしいものが見当たらない……。
ところが、マーヤが立つとチャイムの音とともにあっけなく開いてしまった。どうやら、フューリーのゲートや神殿の通廊にあったのと同じ、妖精の指紋にあたる羽のパターンを認識する照合装置が、どこか見えないところに備えてあったらしい。よもや立往生かと内心焦っただけに、彼女に来てもらったことを朋也は感謝した。ミオはかなりムスッとしてたけど……。
「以前もこの塔に入ったことがあるのか?」
先頭に立って乗り込んでいくマーヤに声をかける。
「ううん。紅玉の封印が解かれてからは、神獣様はエメラルドのアニムスを誰の目にも触れさせなくなったしぃ……。いまこの〝蚕室〟に入ることを許可されているのは、レゴラスの妖精長と次長2人の、SSクラス3人だけよぉ」
「蚕室?」
「あたしたちの間では、このアニムスの塔のことをそう呼んでいるのぉ。アニムスを保管する以外に何か意味があるのかは知んないけどぉ……」
「いまマーヤが入ってこれたのは、やっぱりフューリーの妖精長に昇格したからなのか?」
「たぶんねぇ」
肩をすくめてみせる。じゃあ、マーヤにとってもこの扉の向こうは未知の場所なんだな……。キマイラやレゴラス派と敵対する立場にある彼女の通行許可があっさり降りたのは、不思議といえば不思議だ。こっちとしちゃ助かったけど。
一行が扉をくぐり抜けて塔の中に足を踏み入れると、そこにはまたもや驚くべき光景が広がっていた。塔の中には壁や天井がなく、上下左右に宇宙が広がっていたからだ。青白い光を放つ銀河や星雲が、手が届きそうなほど近くにあるように見える。この神殿は、建物と異空間が入れ子状の構造になっているらしい……常識ではとても理解できないけど。なぜか皆既日蝕のコロナだけは星空の一角でほのかに輝いていた。
その星々を背景に、1本の階段が螺旋を描きながら上に向かって伸びている。階段の左右には水晶のように輝く柱が1列ずつ伸びていた。
碧玉が保管されているのは塔の最上部で、紅玉の再生実験もそこで行われているはずだとマーヤは請合った。千里の居場所もそこだろう。上を見上げると、なるほど階段の終点の辺りで赤と緑の光がチカチカと瞬いているのがわかる。
階段を登っているとき、朋也は階段の両脇に並んでいる水晶のように透き通った柱状の物体に何気なく目を向け、足を止めた。さっきから何か丸っこいものが中に入っているのはわかっていた。単なる飾りだろうと思い最初は気にも留めなかったのだが、柱の中味が1つ1つ微妙に異なっているのに気づく。
透き通っていた球形の物体は、上に向かうにつれて次第に琥珀色に濁り始め、形も細長く円柱状に伸びていった。表面には影が映り、中に別のものが入っていることをうかがわせた。一種のカプセルらしい。当初は神殿の入口にあったようなアニムスのレプリカかと思ったが、むしろ何かの生きものの卵のように見受けられる。
ジュディにどやされたこともあり、立ち止まってじっと観察しているわけにもいかないので、一行は再び階段を登り始めた。螺旋を1周ほど巡ったとき、水晶の中の奇妙な陳列物に明確な変化が現れた。
「何これ? 芋虫さん?」
クルルが首をひねりながら水晶の中味をながめる。
少し前から球にひび割れ状の模様が目立ち始めていたが、やっぱり卵だったのがこれではっきりした。これは明らかに生物の一種、昆虫の幼虫だ。精巧な作り物かもしれないが、どちらかといえば剥製かホルマリン付けの標本のような印象を受ける。
ただ、朋也はこのような昆虫を知らなかった。何しろサイズがでかい。全長50センチほどで、奥に進むほど大きくなっていく。クレメインで神木にとりついた巨大アリを退治したが、あれはモンスターで実体はない。中生代に繁栄した巨大ヤンマのヤゴだったらこのくらいあってもよさそうだが……。
奇妙なのは大きさばかりではなかった。表面に種々の奇妙な突起が見られるのだ。分類を決定する要素とはあまり無関係な装飾なのかもしれないが、三葉虫やアノマロカリスのイメージに近い。しかも、それらの突起は色や形状が水晶の中の個体によって千差万別だった。
「ある種の昆虫を成長過程に沿って陳列したように見受けられますね」
「気色悪……。キマイラってホントに悪趣味ニャンだニャ~」
ミオ……俺は前駆形態時代に、○○○リの足をくわえたお前を目撃したことがあるんだが……。
それにしても、なんでこんなものがアニムスの塔なんかに並べられているんだろう? 朋也は胸のうちに言い知れない不安を感じていた。〝蚕室〟か……。マーヤは標本の並ぶ階段を登り始めてから、口をつぐんで何も言わない。
一行はさらに螺旋階段を最上階目指して登っていった。神殿本体に入ってから玉座までの空間と違い、ここにはモンスターは出現しなかった。ただ驚いたことに、遠くに輝く銀河や星雲と思われたものは、実はホントに手の届くところを漂っているミニチュアだった。それどころか目の前をついと横切ったりもする。見た目は天文写真で見るような銀河そのものだし、模型だとしても何でできてるのかさっぱりわからない。うっかり触ったら、いきなりバシッと音がしてルビーの炎が燃え上がった。
「な、何なんだ、これ!?」
火傷しそうになった手を引っ込めて目をパチクリさせる。
「おそらく、それはアニムスのかけらでしょう」
フィルが答えた。
「かけら??」
彼女の説明では、世界の法則を司るアニムスは、始原の宇宙の歪みから生じたエネルギーが形をとったもので、最初はこんなふうにバラバラだったらしい。それが最終的に紅、碧、蒼の三つの性質を持つ宝玉の形にまとまったのだとか。再生の儀式を執り行ったこのアニムスの塔の中は、どうやらその原初の状態を一時的に再現しようとしているらしい。何だかよくわからないが、ともかく朋也はそれ以降ミニチュア銀河には近づかないことにした。
「ニャハハ♪ 鉱石がザックザクニャ~。これであたいはアニムス長者よん♥」
後ろでミオが欠片をひっぱたいて大量の鉱石を手に入れていた。
「あ、クルルのは触ったらHPが回復したよ♪」
……。どうやら朋也は単に運が悪かっただけらしい。
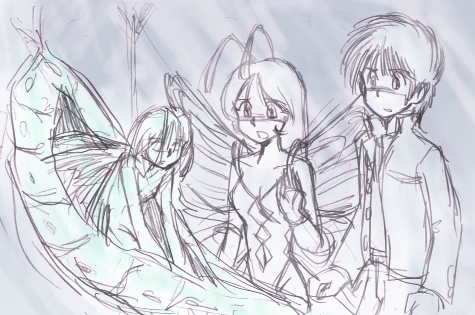 水晶の中の謎の昆虫のほうはといえば、1メートルほどまで成長した後、繭を作り始めた。やはりフィルの指摘したとおりだ。とすれば、もう少し先へ進めばおそらく成虫の姿を拝めるはずだが……。
水晶の中の謎の昆虫のほうはといえば、1メートルほどまで成長した後、繭を作り始めた。やはりフィルの指摘したとおりだ。とすれば、もう少し先へ進めばおそらく成虫の姿を拝めるはずだが……。
はたして、最上階まで後3周あまりになったとき、一行は水晶の中に驚愕すべきものを目撃した。繭を破って上半身をのぞかせていたのは、なんとCクラス時代のマーヤにそっくりの妖精だったのだ──
一行は全員その場に立ちすくんだ。皆は否応なくマーヤと〝標本〟の個体を交互に見比べた。
しばらく呆然として、自分そっくりの妖精が変態を遂げて羽化した瞬間を捉えた標本を見据えてから、マーヤは泣き笑いの表情を浮かべて仲間たちを振り向いた。
「エヘ……ヘ……子供の頃の記憶がないなんて、道理で変だとは思ってたけどぉ……あたしたちの正体って、実は虫さんだったのねぇ~~」
もしかして、昆虫が進化して成熟形態の地位を獲得したのが妖精……ということなのか? だが、エデンで文明社会に参加している成熟形態の約800種族の大半は脊椎動物、それも哺乳類と鳥類が占めていた(ポートグレーにはイカ族がいたけど……)。節足動物は1種もおらず、3神獣と神木の共同所管の扱いになっていたはずだ。彼女たちが、他の成熟形態の種族に奉仕する半分奴隷に近い存在であることも併せると、腑に落ちないことは山ほどある。真相を知っているのは、キマイラと入室を許されていたSSクラスの数名の妖精だけだろうが……。
マーヤはげっそりした表情で朋也の顔を恐る恐る見上げた。
「朋也ぁ……これがあたしたちでも……あたしのこと、まだ好きぃ?」

