3 朝ご飯
目が覚めてみると、私は猫のままだった。
絶望感がどっと押し寄せてくる。レース中、第一ハードルでいきなり足引っかけて転倒したみたいな、最悪の気分。布団があれば、カメみたいに頭まですっぽり潜っていたいところだ。あいにく、汚い路地裏みたいなこの場所には、座布団一枚さえない。
寒さはもう感じない。筋肉の強ばりもとれた。けれど、心はずっと寒いままだ。気分爽快にはほど遠い。夕べもし、リューイがいてくれなければ、もっとひどいどん底気分を味わっていただろう。
リューイ? そうだ、彼はどこにいるんだろ?
辺りはもうすっかり明るくなっていた。見回してみたけど、彼の姿はどこにもない。
ひょっとして、私を置いたままどこかへ行っちゃったのかな? せっかく仲良くなれたのに……。
せめてお礼の一言、お別れのあいさつでも交わしてから、さよならしてもいいじゃない。けど、なんだかんだ言っても、しょせん相手は猫──。
と思っていたら、彼の姿が入口に見えた。口に何かをくわえている。
ネズミだ──。
彼は私の手前まで来ると、そいつをポタリと地面に落とした。
ひぃぎゃあああっっ!!
私はその場で一メートルくらい飛び上がった。
ネズミが苦手っていうわけじゃないけど、ともかく死体は私、ダメなんだよ~。
「どうしたの?」
リューイはキョトンとした顔つきで私を見ながら言った。
「いいよ、遠慮しなくて。自分の分は後で獲ってくるからさ」
……つまり、これは私の朝ご飯ってこと!?
彼の視線は私の顔と足もとのネズミとを交互に行き来している。
そうなのね、やっぱり……。
猫に対する好感度がまた一ポイント下降してしまった……。
無理。絶対無理。他のことなら何でもするけど、ネズミだけは勘弁してほしい。むかし図書館で借りた本に、男の子が猫になっちゃうお話があって、その主人公の子はイヤイヤながらネズミを食べちゃってたけど、私はそんなの無理。
リューイは私の戸惑う様子を見て、少し考えこんでから、また口を開いた。
「ふむ……きみはどうやらネズミを口にしたことがないらしいね。狩りの練習さえしたことがないとみえる。人間の親にそれを求めるのは酷な相談だろうけど。しかし、食べ物の範囲を制限してしまうのはあまり感心しないな。外で暮らす身であれば死活問題につながる。しかも、ネズミはぼくらの基礎食糧だ」
……。そんなことは百も承知です。でも、私は猫じゃないんだ……。
私がなおも目を背けていると、リューイはあきらめ顔で言った。
「まあでも、きみの場合は、そういう決心で家出をしたわけじゃないだろうし、健康で長生きするという目標があるなら、〝外食〟はあまりお薦めできないがね。きみが固辞するのであれば、ぼくが自分でいただいてしまうけど、かまわないかい?」
私は二つ返事でうなずいた。
リューイはネズミを頭からムシャムシャと食べだした。いとも自然に。
彼がおいしそうに獲物をほおばる様子を、横目でうかがっているうちに、次第に彼に対して申し訳ない気持ちが湧き起こってきた。
リューイは私より先に起きだして、きっと私のお腹がペコペコだろうと思って、わざわざご飯を用意してくれたに違いない。一所懸命捕まえてきてくれたのに。まあ、彼にとっては、ネズミ一匹捕まえることくらい、それこそ朝飯前かもしれないけど……。
なのに、私ったら、あからさまにいやな顔をして、せっかくのお土産を突き返しちゃったんだ。
虫だとか、何とかの脳ミソとか、猫とか、世界にはそんなものを食べる人たちもいる。まあ、人間の場合は不自然なものばっかり食べてるのかもしれないけど、動物たちは違う。ずっとずっと昔からの自然の定めに従って、自前の爪と牙で手に入る獲物を食べてるだけだ。それを私たちがいちいちキャーキャー悲鳴をあげるのは、おかしな話だよね。みんなそうやって生きてるんだもの……。
「ごめんね。せっかく持ってきてくれたのに……」
面目なさげに謝ると、彼は気にしてないというふうに答えた。
「いやいや。二回行く手間が省けたし」
「……それ、おいしい?」
恐る恐る聞いてみる。
「うん。なかなかいける。今日の収獲はやや小ぶりだったけど、小太りで肉づきも悪くないし、味も──」
「か、解説しなくていいから!」
あわてて遮った……。でも、確かに、なるべくまっすぐ見ないようにしつつ、彼が食べる様子を観察すると、さもおいしそうだ。
「ちょっと味見してみる?」
恐々と視線を送る私に、リューイはもう一度尋ねた。
「え、遠慮する」
首をブンブンと横に振ったけど、言葉とは裏腹にお腹がぐうと鳴る。もちろん、人間のままの私だったら、そんな食事風景を目にするだけでげんなりして食欲を失うところだ。けど、この身体の持ち主の本能は、それとは正反対の反応を示した。私自身も、昨日の給食の後から一口も食べていないから、空腹度はマックスだったけど……。
ネズミのご馳走はもはや尻尾を残すばかりとなった。
「ごちそうさまでした。……さて、そうは言っても、このままではきみもお腹が空きすぎて、お腹と背中の皮がひっついて三味線みたくペッタンコになっちゃうだろう。いつもはどんなものを食べてたの? ドライ? それとも缶詰? 銘柄とかは決まってた?」
返答に詰まる。
「えっと、そのぉ……お母さんが作ってたの……」
リューイはそれを聞いて目を丸くした。
「へえ……そいつはすごいや。自家製のキャットフードを用意してくれる人もいないわけじゃないけど、最近はこの国じゃかなり稀少な人種だよ。いや、たいしたもんだ。きみが人間を自称するのもうなずける」
……。いままで以上に大きな誤解だけど、話がややこしくなりそうだから、とりあえず訂正はしないでおく。
「参ったな……。長く野外生活を送っていると、二、三日くらい飯抜きでも平気になってしまうものだけど、きみにはやっぱり辛いだろう。少しでも口に何か入れたほうが、気分も落ち着くはずだしね。何かリクエストとかある?」
リクエストと言われたって、野良猫の口に入るもので、私が食べられるものなんてあるわけないよ~。
「生ゴミ系は? 早朝だったらまだ鮮度も落ちていないんだが」
「論外」
「虫とか。甲虫やイモムシなら多少は腹の足しになるし。タンパク源としても良質だ」
「ネズミ以上に無理」
「ううむ……」
ぜいたく言って困らせてるのは、わかってるんだけどね……。
「新鮮なキャットフードなら問題ないかい?」
猫の身で飢えずにすむためには、そこら辺で妥協するしかなさそう。スナックだと思って目をつぶれば大丈夫よね。材料に何が使われてるかなんて、この際考えないほうがいい。これ以上駄々をこねて、リューイに愛想を尽かされるよりはマシだもの。いま、彼というアドバイザーを失って、この先一匹でやっていける自信はない。
「うん……」
「よし、いい子だ。じゃあ、知り合いに拝み倒して、お相伴に預からせてもらおう。困っているときはお互いさまだからね」
「恩に着ます、う~……」
私は深々と頭を下げた。
「じゃあ、ちょっとついてきてくれるかな?」
食後の身だしなみにヒゲをこすりながらしゃべっていたリューイは、おもむろに両前足を伸ばして柔軟体操をすると、手近な箱の上にヒラリと飛び乗った。そのままトントンと箱を伝って出口へ向かっていく。私も彼の後に続いて外へ。
「つかぬこと聞くけどさー、猫が顔洗うと雨が降るって本当?」
後ろを歩きながらリューイに質問する。
「それは確かに予想外の質問だね……。まあでも、世の中のできごとにあれこれ関心を抱けるだけの心の余裕があるのは、いい徴候かもしれないな。何事にも興味を持てなくなってしまうよりずっといい」
リューイはそう言ってかすかに微笑んだ。
彼の指摘したとおり、夕べに比べればだいぶ心にゆとりが出てきたと思う。何気ない会話が交わせるようになったのがその証拠だよね。それもこれも、さりげなく私に気を遣ってくれる彼のおかげだけど……。
「それはともかく、さっきの質問に対する答えは、残念ながらぼくにはわからないなあ」
「全然思いつかない?」
なんだ。じゃあ、やっぱりただの迷信かなあ?
「いや……湿度や気圧の変化を感じて、なんとなくソワソワと落ち着かない気分になって毛をなめてみるとか、そうした行動をとる猫はたぶん多いと思うよ。具体的にどのくらい毛づくろいの回数が増えると雨になるかは、ちょっと見当がつかないな。大勢の猫に聞き取り調査をして統計でもとるか、あるいは、だれか一匹の猫の行動を毎日観察し続けて、雨の日と晴れの日で顔を洗う頻度を比較してみないことにはね。まあ、日々の身だしなみを怠りがちな者を観察対象に選ぶほうが、気象予報の目的にはかなうんじゃないかな」
プッ……彼の気取った言い方に、私は思わず吹き出してしまった。
「アッハハ! おかし……。リューイって、なんだか学者みたい」
「変かな?」
「変。絶対変」
何しろ、彼の口ぶりときたら、まるで猫科専門の動物行動学者みたいなんだもの。まあ、人類にも人類学者はいるから、不思議じゃないかもしれないけど。
なおも笑い続ける私に対し、リューイは気分を害するでもなく、ちょっと首をかしげて言葉を続けた。
「そうか……。でも、ぼくら猫っていうのは元来、学究肌の動物といっていいからね。時間のすごし方からして学者向きだ。おとなになれば、ぼくらはウロウロと動きまわって無駄に体力を消耗したりはしない。狩りとテリトリーの巡回に出ている間以外は、腹ごなしを兼ねて専ら休息に当てる。半ばまどろみつつ、自分の心の内側を深く探ってみたり、世の中の理について思いをめぐらす。ネズミやなんかは、始終あくせく食べ物を貯えたり、警戒することに時間を費やして、ものごとを掘り下げて考える余裕はない。犬の場合、彼らの主要な関心事は群れの内外の力学だ。そこへいくと、猫はだれしも生まれついての学者といえるかもね」
そうなんだ。確かに、猫って何考えてるかわかんないようでいて、独特の知的な雰囲気をまとってるよね。この間のでかいモップ猫だけは、とてもインテリには見えないけど。
「それにしても、ぼくに言わせれば、ユニークなのはきみのほうだよ。きみはときどき、自分が猫じゃないみたいな話し方をする。考え方そのものが、ぼくらの標準からずれている。まあ、育ちの問題だろうけど……」
私は内心ビクッとなった。いまこの時点で、自分が本当に猫じゃないことを彼に知られるのはまずい気がした。ここはひとつ、照れ笑いでごまかすことにする。
「で、リューイはどっちのほう?」
「ぼくは猫の気象予報士には向かないほうだと思うね」
私はクスリと笑みを漏らした。ずっと外で暮らしているらしいのに、彼のビロードのような黒い毛皮は美しさと清潔さを保っている。雨だろうと晴れだろうと変わりなく、日ごろ念入りに手入れしている証拠だろう。
私たちは移動を再開した。
夕べは気づかなかったけど、私たちが一夜をすごしたのは、どうやら倉庫代わりに使われている店の脇の狭い通路のようだった。そこら中に、段ボールや発泡スチロールのトレイが無造作に積み上げられている。
店の表側に回ってみると、シャッターは閉めきりになっていた。破れかけた張り紙に、〝永年のご愛顧ありがとうございました〟と書かれている。たぶん、大きなスーパーとの競争に負けて閉店した、昔からのちっぽけな商店だろう。
これで、現在位置がどの辺かもだいたいわかった。
リューイが足音一つ立てず、ヒラリと塀の上に駆け上がった。
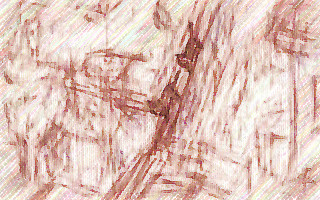 私も彼の後に従いジャンプ。人間でいえば、三階建ての学校の屋上まで、壁伝いで一気によじ登るようなものだ。最初だけちょっとためらったけど、やってみるとうそみたいに簡単だった。例えるなら、跳び箱の四段目くらいのあっけなさ。月面じゃないけど、重力が小さくなった感じ。
私も彼の後に従いジャンプ。人間でいえば、三階建ての学校の屋上まで、壁伝いで一気によじ登るようなものだ。最初だけちょっとためらったけど、やってみるとうそみたいに簡単だった。例えるなら、跳び箱の四段目くらいのあっけなさ。月面じゃないけど、重力が小さくなった感じ。
猫に対する好感度、1ランクアップ。
塀の上の猫専用歩道を、リューイの真後ろについて歩く。
とりとめのない会話を交わしているうちに、目的地に到着。平屋の小さな家が密集している一角だ。そのうちの一軒のせまい庭に入ると、リューイは家の中に向かって声をかけた。
「マリ、いるかい?」
「マリちゃんっていうんだ。私の友達とおんなじ」
「え? きみにも猫の知り合いがいたのかい?」
わ、またポカやっちゃった。
「あ、ううん、違うの。ええっと……人間の友達なんだ」
「なるほど。〝お母さん〟の友達が家に遊びに来るんだね」
「そ、そんな感じ……」
ほどなく現れたのは三毛猫のメスだった。そういえば、三毛ってみんなメスばっかりだってどこかで聞いたっけ。年齢まではよくわからないけど、私が体を借りてる〝この子〟より年上なのは間違いない。
「だれかと思えばリューイじゃない。しばらく顔を見せないと思ったら、急に訪ねてきたりして、相変わらずの風来坊ぶりだこと……あら?」
そこでマリさんは私に視線を移した。
「こ、こんにちは」
私がオドオドとあいさつすると、マリさんはクスクスと軽やかな笑い声を立てた。
「まあ、ずいぶんかわいらしいガールフレンドだこと」
む~、なんかバカにされてるっぽい。まあ、〝この子〟はまだ一歳くらいだろうし、私自身も一四の小娘だけどさ。
「どうしたの、今日は? お客さん同伴で」
「うん。ちょっと頼みごとがあるんだけど。この子、今日初めて外出なんだよね。表の食べ物が合わないみたいでさ。フードを分けてもらえないかな?」
「あらあら、かわいそう。じゃあ、特別におうちに入れてあげるわ。ついてきて。いまうちの人いないから、安心していいわよ」
リューイに促され、マリさんの後に続く。
彼女は給湯器らしい四角い箱の上から、小さな天窓に向けてヒョイと跳んだ。マリさんのために開けっ放しにしてあるようだ。ずいぶん不用心だなあ。まあ、人間の泥棒にここをくぐるのは無理か。
「おじゃましまーす」
バランスをとりつつ、お風呂場の下に着地。開けっ放しの戸をくぐり抜けて先に進むと、すぐに玄関と台所につながっていた。勝手に他人の家にあがるのは気が引けたけど、猫なんだから別にいいよね。
マリさんのそばへ行くと、猫砂のトイレの手前にピンク色の器が置いてあった。中には星型のドライフードが円錐形の山を築いている。この家ではご飯を常備してくれてるんだろう。大助かりだ。
「こんな粗末なものでよかったら、どうぞ召し上がれ。用意したのは私じゃないけど」
「すみません、ほんとに。それじゃ、お言葉に甘えさせていただきます」
さっそくカリカリにパクつく。予想してたとおり、スナック感覚でなんとか食べられる。サカナの匂いはきついけど。
「ケホッ!」
カリカリのかけらが気管に飛びこみそうになり、私は思わずむせ返ってしまった。
「あらあら、そんなにあわててかきこまなくたって、なくなりゃしないわよ。よっぽどお腹が空いていたのねぇ」
マリさんがあきれ返って言う。
「リューイもよかったらいかが?」
「ぼくはもう食事はすませてきたから」
器の中でみるみる減っていくキャットフードを前にしても、マリさんは別にうらめしそうにするでもない。家にあがりこんで彼女のご飯を失敬している、知って間もない野良猫の私に、温かな眼差しを注いでくれている。ご飯を食べ散らかすこどもたちを、目を細めてながめている幼稚園の保母さんみたいに。
「ごちそうさまでした」
自制するつもりだったのに、皿の上のフードはもう半分も残っていない。飼い主の人にマリさんが怒られなきゃいいけど……。
「ありがとうございました」
「ありがとう、マリ。助かったよ」
二匹で頭を下げると、マリさんはリューイに向かってウインクしてみせた。
「また今度デートに誘ってちょうだいよ」
「いいとも」
マリさんの家からの帰り道、私は彼女のことをずっと考えていた。
リューイの口から〝困ったときはお互いさま〟なんて、今月の学校の標語みたいな台詞が飛び出したとき、私は意外に感じたものだ。犬も猫も、助け合いや譲り合いの精神とは無縁だって思っていたから。でも、マリさんも、リューイも、赤の他猫にすぎない私に救いの手を差し伸べてくれた。この間のブタ猫みたいなやつが例外で、本当は猫っていいやつのほうが多いのかも……。
「ねえ、リューイ。変なこと聞いていい? マリさんにはほんとに感謝してるんだけど、どうして彼女、会ったばかりの私にご飯を分けてくれたのかな? 言っちゃ悪いけど、私、猫ってもっとガツガツしてて、よそ者にお裾分けしたりするわけないと思ってたよ」
彼に向かって疑問を口にしてみる。
「まあ、ガツガツしてるやつも確かに多いけどね……。でも、マリは食が細くて、一回の食事量をセーブできるタイプだし、何より母親を経験してるから」
そっか。そんな気がしてたけど、あのときのマリさんのやさしい目つき、やっぱりお母さんのそれだったんだ。
とすると、リューイはひょっとして、お父さん気分で私に接してるの? 猫の場合、父親はこどもの面倒を見ないって聞いた気がするけど……。
「ところでさ。マリさん、リューイにあんなこと言ってたけど、あなたとはどういう関係なの? カノジョ? 母親っていうからには、まさかダンナだったり?」
「デートの話? いや、もちろんさっきのはほんの戯れさ。彼女のパートナーはフルフルなんだ。大柄なヒマラヤンで、この界隈じゃいちばん女の子にモテる」
「ヒマラヤン? ……もしかして、毛がモップみたいにクシャクシャできったないやつのこと?」
「え……会ったの、ひょっとして?」
私はリューイに会う直前に、フルフル氏に体よく追い払われた顛末を語って聞かせた。
あのモップ猫がメス猫の人気ナンバーワンだなんて、とうてい信じられない。どうしてあんなデリカシーに欠ける乱暴なやつがいいわけ? 顔だってつぶれて不細工だし、おまけに真っ黒けだしさあ。真っ黒っていっても、リューイみたいにきれいな黒毛じゃなくて、まるで煙突掃除でもしたみたいに汚れて真っ黒になったやつなんだよ? リューイのほうが断然かっこいいじゃん。
全身の毛をピンピンと毛羽立たせて憤懣をぶちまける私に、リューイは苦笑しながら言った。
「おやおや、それは災難だったね。多少ガラの悪いところはあるかもしれないが──でも、女の子たちに言わせれば、そこも魅力のうちなんだけどね──根はいいやつなんだ。たぶん、寝入りばなに起こされたもんだから、虫の居所が悪かったんだろう。悪気はなかったんだよ」
「フルフルはきっと典型的なガツガツタイプでしょ? 絶対他猫に自分のご飯なんてあげそうにないもん」
「……うん、まあ」
「ともかく、あいつの顔なんて二度と見たくないや」
しゃべりながら歩くうちに、私たちは砂利石の敷き詰められた駐車場にたどり着いた。この場所にははっきりと見覚えがある。家から駅に向かう途中にあって、自転車でよく通りかかるところだ。
「さて、どう? そろそろ自分の地図を描けるようになってきたかな? 家まで帰れそう?」
「うん。大丈夫、と思う……」
昨日は猫に変身した初日だっただけに、パニックに陥っちゃったけど、猫の感覚にもだいぶ慣れてきた。
ここはいつもの、私の住んでいる町だ。家に帰るのに迷うこともない。
私の様子から、リューイもそう判断したんだろう。けど……いざお別れとなると、言葉とは反対に心細さが募ってくる。
「自動車にはくれぐれも気をつけてね。大体、交通事故に遭うのは表に出て日の浅い若い子と相場が決まってるんだ、きみみたいなね。道を横切って渡るときは、車が通りそうかどうか、足の裏で感じる震動で判断するんだよ。いいね?」
「うん。わかってる……」
「そうか……。なら、安心だ」
少しの間、リューイは優雅な仕草で前足の爪を噛んでいたが、それからやさしい目で私をじっと見つめた。
「家の中での暮らしも悪くはないと、ぼくは思う。物事を考えるための時間はたっぷりあるし、何より安全だからね。きみが自宅に戻って、〝お母さん〟のそばで一生を送る選択をしたとしても、ぼくはそれを尊重したい。けどまあ、ホームレスの生活も、まんざら捨てたものではない。外の世界を知ることは、自らの思索に深みを与えてくれるものだ。何より自由があり、出会いがある。きみが家に帰ってからも、ぼくやマリのことをときどき思い出してくれるとうれしいな。フルフルのことも、ね」
「うん……」
私の気持ちを和ませようと、冗談めかして言ってくれたのはわかってる。けど、私はしょんぼりとうつむいたまま、あいまいに返事をすることしかできなかった。
「じゃあ、気をつけていきたまえ。さよなら」
そう言い残して、リューイは駐車場を囲む塀の上に飛び乗り、歩き去っていった。
彼の後ろ姿を見送りながら、私はため息をついた。
あ~あ、また独りぼっちになっちゃった……。
隣のアパートの植えこみの影に消える直前、リューイはもう一度こちらを振り返った。
「もし、また何かの事情で表に出てしまったら、ここへ来てぼくの名を呼んでおくれ。きっと会いに来るから」
「ありがとう、リューイ。またね……」
彼の姿はすぐ見えなくなってしまった。


