4 リセット
私は駐車場の真ん中に一匹ポツンと残された。
しばらくぼおっとしていて、ハッと我に返る。
しっかりしろ、栞。いつもの私らしくないぞ。
頭にコチンと手をやろうとしたけど、うまくいかないで、いわゆる猫の顔洗いのポーズになってしまった。リューイのほうが私より前足の動作が巧みでエレガントだったなあ。私、人間出身なのに……。
ともかく、いったん家へ帰って、〝私〟がどうなったのか見てこよう。お母さんたちにも会いたいし。
もし、〝私〟を見つけたとしても、はたして猫になった私が元の身体に戻れるのだろうか? 先のことを考えると、不安でたまらない。けれど、いまはまず〝私〟の無事を確認することが先決だ。
太陽はだいぶ高く昇っていた。時計がないからわかんないけど、もう正午を回っていそう。夕べはいろいろあって、疲れてもいたし、朝起きた時点でお昼に近かったんだろう。
今日は水曜日だから、みんなはいまごろまだ授業中のはず。確か五時限目は鈴木先生の英語だっけ。ラッキー♪ と言いたいとこだけど、なんだか教室を脱け出してサボってるみたいで後ろめたい。
でもまあ、本物の私はたぶん病院行ってことで、無断欠席扱いは免れているはずだ。だったら、せっかくの解放感をたっぷり味わっとかなきゃ損だよね。猫の姿で町内をぶらりと一回りしてみようかな……。
そう思った私は、お散歩気分でフラフラと寄り道しつつ、ゆっくり自宅へ向かった。家に到着したのは、もう日が傾き始めたころだった。
ひょっとしたら、ズルズルと時間を延ばしてきたのは、現実に直面することを内心恐れていたせいかもしれない。
次の辻のところを曲がれば、もう私の家は目と鼻の先──というところまで来て、私は異変に気づいた。
何かが私の心をぐっとわしづかみにして離さない。
匂いだ。敏感になった猫の鼻に、ふだん嗅ぎ慣れない多くの匂いが家のほうから漂ってくる。
大勢の人の匂い。私がごくたまにしか会うことのない、あるいは、一度も会ったことのない人たちの匂い。
消毒薬っぽい匂い。病院の匂いみたいな。
何かの焼ける匂い。これは……お香? お線香の匂い?
音も聞こえる。ヒソヒソいう話し声に混じって、だれかのすすり泣く声がする。規則的に何かをたたく音。そして奇妙に尾を引く歌みたいな声。これは……そう、お経だ。
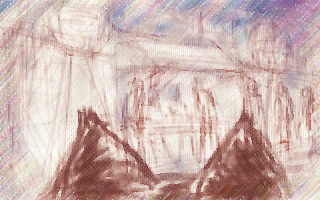 植え込みの影からそっとのぞくと、玄関前の路上に仮設テントや椅子が並べられていた。両側には花輪が並んでいる。
植え込みの影からそっとのぞくと、玄関前の路上に仮設テントや椅子が並べられていた。両側には花輪が並んでいる。
その前を、黒い服を着た人たちが通り過ぎ、門をくぐって庭へ入っていく。私の知っている近所のおばさんたちや、親戚の人もいる。
私の家で、だれかのお通夜が行われているんだ。
庭に回ると、窓が開け放たれた客間の奥に、チラリとよく見知った顔が見えた。お父さん、お母さん、大。
お母さんはたびたび真赤に腫れた目にハンカチを押し当てていた。お父さんはひどく疲れた表情で、ときどきお母さんの背中をそっとさすっている。大は、アイテムコンプリートしたRPGのセーブデータを私が誤って消しちゃったとき以上のものすごいしかめっ面だ。
正面には、たくさんの花に囲まれた人一人入れそうな箱。そして、大きな写真が飾ってある。遠くてよく見えないけど、白いブラウスを着た少女が、この場にちっとも似つかわしくないはつらつとした笑顔をふりまいている。
私の遺影。
死んだのは私だった。私のお通夜なんだ、これ。
めまいがした。頭をガンとなぐられたみたい。それも、金属バットかでっかい壺でもって、おもっきしガツンと。
けど……それは予期していたことだった。やっぱりあのとき、私は事切れていたんだ。ダメだったんだ──。
うそだ、うそだ、うそだ・・・・
夢だ、夢だ、夢だ・・・・
長い夢。とてもリアルな夢。いつまでたっても覚めない夢。
それでもいいから、夢であってほしい・・・・
私は人目を避けるように、物置の陰で縮こまっていた。
夕べ、私は自分の死体を前にして、いったんは覚悟を決めたつもりだった。でも、今日、改めて自分のお通夜が開かれるところを目の当たりにすると、再びさまざまな感情が次から次へと押し寄せてくる。
熱を出してお母さんに一晩中看病してもらったこと。運動会のリレーでテープを切ってから、ビデオを撮るお父さんに向かってガッツポーズを決めたこと。大とはほとんど毎日のようにケンカしてたな……。誕生日のパーティー、お盆休みに出かけた家族旅行……アルバムをめくって一枚一枚の写真をながめるように、それらの懐かしい思い出が脳裏をよぎっていく。
でもいま、アルバムそのものを捨て去るときがきたみたい。私は人間をやめちゃったんだもの──。
もう進路で悩むことも、大会で入賞するとかそういう目標に向かってがんばることもない。お笑い番組もトレンディードラマの最終回も観れない。学校へ行って友達とおしゃべりしたり、メールを交換することもない。テストや宿題でさえ、いとおしく感じる。
いままでずっと当たり前だと思っていたものが、すべて二度と手の届かないガラスの壁の向こう側に置かれてしまった。毛で覆われ、へんてこな肉球のついたいまの私の前足じゃ、決して触れることのできないところへ。
その代わり、これからの私に用意されていたのは、まったく別の人生──いや、猫生だった。
冷たい雨の日も、雪の日も、台風の日も、布団どころか屋根さえない宿無しの生活を強いられ、車や犬にビクビクしながら、お腹を壊しそうなものでも飢えをしのぐために口にしなきゃならない。病気になってもお医者に行けないばかりか、だれも看病してくれない。
最後にはきっとろくでもない死に方をするんだろう。こうやってお通夜や葬式を開かれることもなく、だれにも看取られず、廃屋の床下とかでひっそり寂しく──。
思いっきり泣き叫びたい。けど、相変わらず涙は出てこない。泣きたいのに。自分が死んでしまったというのに。泣くことができない。
またしても猫の身が恨めしくなる。これまでたまった好感ポイント、全部返上してもいいから、人間に戻りたい……。
「栞……」
声に振り向く。いま、この〝私〟に向かってその名を呼んでくれるのは一匹だけ。
私が無事に家にたどり着けるかどうか、やっぱり気になって、こっそり後を尾けてきたんだろう。
リューイは私のことをじっと見つめた。さっき別れたときまでとは全然違う目で。
「……ここが……きみの家だと言ってる?」
私は返事をせず、うなずくこともせず、ぼんやりと彼を見つめ返した。
「この家には……猫はいない。いままでに猫が生活していたという形跡もない。ここに猫は住んでいなかった……」
私はなおも黙っていた。彼も返事があることを期待してはいなかったろう。
「きみの言ったことは本当だったんだね? きみは……きみが自分を人間だと言ったのは、そういう意味だったんだね……」
「わかったでしょ? あなたには私のために何をすることもできないの。もうどこかへ行ってよ。行っちゃいなよ。私のことなんかほっといてさ。どうだっていいじゃない、私は猫じゃない。もう人間でもないけど……」
声にならない声で訴える。
二匹の間にただ時が流れる。残酷に過ぎ去っていく。
私は彼が立ち去るのをじっと待ち受けた。
けれど、リューイはどこへも行かなかった。じっと私のそばにいてくれた。
それこそが私に残された唯一の慰みだと、一握りの希望だと、知っていてくれたから──。


