4 初勝利
ミオに誘われ、俺たち三人は買い物に出かけることにした。
いくらメタコスモスでは魔法が使えるといっても、指をパチンと鳴らせば何でも欲しい物が宙に現れる──という具合にはいかない。
魔法とは、歴とした科学的な原理に従ったものなのだ。宇宙の法則に反するまねはできない。魔法を使う際には、俺たちの世界の科学では未だ解明されていないダークマター/ダークエネルギーが消費される。基本的には、化学組成や物理量を変化させたり、生命現象や精神に直接働きかけるものが中心で、あらかじめ構成された物体を無から生み出すような芸当は不得意だ。そんなの一見単純そうな魔法に思えるが、アインシュタインの法則を無視するわけにいかないので、膨大なエネルギーが必要となる。コップ一杯の水を要求するのに、何メガトンもの核爆発に匹敵するエネルギーを消費するんじゃ、さすがに割が合わない。
そういうわけで、必要なものを入手するためには、やっぱりお金を出して買わなきゃいけないのだ。通貨の単位はジーンという。基本の仕組みは、俺のなじんできた貨幣経済と変わらない。ただ、地球の資本主義経済には最近いろいろ歪みが生じていたけど、メタコスモスの星間文明の経済は、モノコスモスでいうなら一昔前の物々交換に近かった。物の値段は、作るのにかかった原材料と労働コストを目安に単純に決められる。だから、いくら航宙船が飛び交うまでにテクノロジーが発達していても、住民の間の貧富の格差は大きくない。ある意味でユートピアといえた。ただ、加工に魔法の力を要する品物を購入しようと思ったら、それなりに値が張ることを覚悟しなきゃならない。
俺たち三人が宿泊しているビスタのホテルの近くには、宇宙港に隣接した大きなショッピングセンターがある。ここでは、各惑星から運びこまれる様々な品が売られている。
センターは大勢の人々でにぎわっていた。他の惑星の多くは、それぞれ構成人口の多数を占める主要な種族がいるが、交易星ビスタはまさに種族の坩堝で、等しくいろんな種族を見かける。
通りを歩く俺の耳に入ってくる雑多な声は、まるで二十のラジオから同時に流れてくる知らない外国語放送のようだ。実を言うと、この世界の住人の使っている言語は、俺には皆目理解できない。
ただし、彼らが俺に向かって話しかけているときは別だ。これは、種族によって千差万別の音声言語やボディランゲージを翻訳する、エスペランサー(言語標準化インターフェース魔法)という超便利な魔法のおかげだ。これさえ使えば、相手の話している言葉が、自分の言語へと自動的に翻訳されて聞こえるわけだ。だから、異種族同士でもコミュニケーションにはまったく不自由しない。
いわゆるテレパシーとは異なり、純粋に言語を変換するだけなので、心の中で思っていることまで相手に伝わるわけじゃない。プライバシー保護の観点からも安心だ。たぶん、この世界のだれもが日常生活で最も頻繁に用いている魔法だろう。
エスペランサーは、話者の一方に多少の魔力が備わっているだけで自動的に発動するため、魔力を持たないニンゲンの俺でも恩恵を受けられる。また、異種族が使用する文字の読解に対しても有効だ。俺はミオたちにいちいち訳してもらわないと読めないけど。ミオとジュディは、PIAのおかげで日本語とネコ族語、イヌ族語をバイリンガルで使いこなせる。
「あ、ほら、トウヤ! あそこ見てチョーダイ♪ マタタビのアロマオイルですって。あたいの部屋と、あと船内の空調システムにもセットしちゃおっかニャ♥」
ミオは気まぐれに店の中に入っては、装備としてはたいして役に立つとも思えない品物をいろいろ物色して回った。さっき俺ともめたことなどすっかり忘れたような顔つきだ。
だが、ジュディはムスッとしたままで、俺とは未だに口をきいてくれない。
しばらくそうやって三人でアーケードの下を歩いていると、不意に首からぶら下げていたゲートキーが黄色く点滅しだした。
コールサイン。近くにいる対戦相手を呼び出す合図だ。他のチームに対して果たし合いを申し込む挑戦状ともいえる。
コールサインのシグナルの色や音はチーム毎に異なるが、何しろ今回が初めてなので、発信しているのが他の六チームのうちのどこなのかは、まだわからない。
「お、おい、どうする?」
うろたえる俺に、ミオはすまし声で答えた。
「とりあえず行くだけ行ってみましょ」
買い物を中断した俺たちは、街角の広大な駐機場に引き返した。
チーム【カンパニー】のスターシップ・セルリアン・ストリーカー号の手前まで来て、すぐ隣に花屋敷の列車みたいなケバケバした宇宙船が停めてあるのに気づいた。エアロックは開いており、昇降機も降りている。そして、地上には四人の小さな人影が。
「あ──っ、来た来たっ! 来たよーっ!」
子供?
「よぉし、いいかい、みんなぁ! いよいよ待ちに待った本番だかんねぇ! 練習どおりにいっくよぉーっ!!」
四人はいったん船の中に姿を消したかと思うと、しばらくして今度は屋根の上にさっそうと登場した。
「チャララ~~♪ チャカラッチャッチャー、ズンチャチャッチャーチャララッ、チャララッチャッチャー♪ パパヤパッパァーッ、ティキティーン、デッデーン、ジャカラッジャカラッジャカラッ、ジャカジャン! チャ~~ン♪ 仮面にぃー輝ぁくー真っ赤なぁー熱いぃ―血―しぃーおーはぁー誓いのぉーしるぅしぃー♪ どこからぁともなくぅーさっそぉーとぉー♪ あらぁーわーれーたぁるはぁー、われらがぁー三きょぉーだぁーいぃ♪ 見ぃたかぁー、ひぃっさつぅー、電光ぉー石火ぁーいなずぅま竜巻斬りパンチィィーッ!(以下略)」
……。相手チームのホストが、どこかで聞いた気がするけどたぶん自作のものと思われる調子っぱずれの主題歌を歌い、クライアント三名が短い手足を精一杯振り回してポーズをとるさまを、俺たち三人はポカンと口を開けたまま見守った。
「いちばんの雑魚だわ」
ミオがボソッとつぶやく。
すぐにわかった。チーム【トリアーデ】だ。ホストの名は藤岡ひろみ。
ちっとも変わってないなぁ……というのが第一印象。
小学校を卒業してから、ひろみは団地から隣町の一戸建住宅に引っ越したため、中学は別々だった。だから、ずっとご無沙汰していたのだが、その間まったくといっていいほど成長しなかったみたいだ。この背丈なら、電車の運賃もこども料金で十分通用するだろう。
外見だけじゃない。中身のほうもそのまんま。昔から特撮マニアで、クラスの女子たちの間では浮いた存在だったっけ。
「相変わらずだな、ひろみ」
「トウヤちゃん、おひさだよぉ♪ でもぉ、今日は手加減はしませぇん!」
「ちょ、ちょっと待てよ。本当に俺たちと戦うつもりなのか?」
戸惑いを隠せずにいる俺に対して、ひろみのほうはやる気まんまんだ。
「あったりきしゃりきぃ! ゲートを開く権利はこの銀河魔法科学特捜超ド級戦隊【トリアーデ】のものなのだぁ! さあ、おまえたち、自己紹介するのですぅ!」
「オッス、リーダー!」
銀河魔法何チャラ戦隊の藤岡隊長の指揮に従い、三人の隊員がいっせいに整列した。
「トリレッド!」
「トリブルーッス!」
「トリピンクですの!」
「三人そろって!」
「銀河魔法科学特捜超ド級戦隊【トリアーデ】!」
「ですの!」
チュドーン!
三人の後ろで三色の火花が華々しく上がる。火薬じゃない、本物の魔法を使った特殊効果だ。戦闘開始前だというのに、そんなところで魔力を消費するのはおそろしく無駄な気もするが。
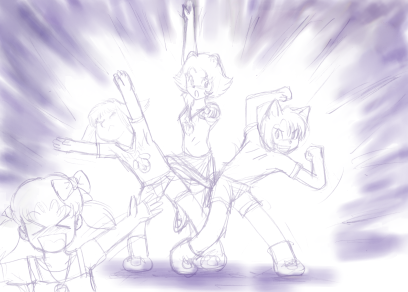
ノリノリで自己紹介をした三人は、それぞれ赤、青、ピンクのスカーフを首に巻いていた。シャツにはモノコスモス時代の顔をかたどったアップリケが付いている。おそらく、ひろみがこの日の晴れ舞台のためにせっせとこしらえたんだろう。
レッド=タロが最近流行りの猫種の一つマンチカン、ブルー=ジロがミニチュア・ダックスフントの中でも最小のカニーンヘン、そしてピンク=ヒメはパスバレーファーム産のフェレット。
【トリアーデ】は七チーム中で唯一、クライアントが三人いる。頭数だけ見ればまさしく最強のチームだが、三人そろってこの足の短さは致命的だ。
「さあ、おまえたち、やっておしまぁい!」
正義の戦隊ヒーローの司令官というより、悪の首領じみた号令をかけるひろみ。
「どうすんの、トウヤ?」
ミオが振り向いて指示を仰ぐ。ジュディも。
でも、俺の心はまだ揺れていた。
「俺は……」
尻込みしている俺を見て、ひとつため息をつくと、ミオはジュディとともに前に出た。
そして、二十分後──。
俺が目にしたのは信じられない光景だった。
「いえーい、完勝だぉ♥」
Vサインを出して勝利ポーズを決めたひろみと三人の子分たちの前で、ミオとジュディは無様に地べたに伏し、息を喘がせていた。
そんな……。
「お、おい、大丈夫か、二人とも!?」
駆け寄ろうとした俺の手を、ジュディが乱暴に跳ねのける。
「触んな!」
「ジュディ……」
呆然とする俺に向かって、ミオが辛らつに言い放った。
「ニャンで負けたかわかる? あんたのせい。ホストのあんたがその気にニャッてくれニャきゃ、クライアントのあたいたちは実力の半分も引き出せやしニャイ。相手がいくらアレだって、勝てっこニャイのよ……」
目の前につかつかとやってきたひろみに、ミオがつっけんどんに尋ねた。
「指定ニャの? それとも開示?」
ここで、ゲームのルールについて解説しておこう。
まず、キーアイテムであるゲートキーについて。大きさはふつうの家の鍵より少し大きめくらいだが、チェーンが付いており、形はブローチかペンダントに近い。真ん中には、宝玉と呼ばれる玉石が嵌めこまれている。
キーには二つのモニターも備わっている。一つにはMPに相当する宝玉魔法の残量が、もう一つにはクライアントのHPに相当する精神力と体力の合計値が人数分のバーで示されており、キーを所持するホストが確認できるようになっている。
現在【カンパニー】が所持しているのは、キャッツアイ、トルマリン、シトリンの三つ。といっても、同じ名前の鉱物でできたただの宝石じゃない。結晶の中に、宇宙空間に遍在するダークエネルギーの一部が凝縮された形で封じこめられている。いわば魔法の素だ。魔法を行使すると、内部のダークエネルギーもそれに応じて消費される。しばらく魔法を使わずにいれば、また次第に溜まっていってもとに戻る。
全部で二十一個あるゲートキーのそれぞれには、別の宝玉が嵌まっており、秘められた魔法の性質も宝玉の種類に応じて異なる。
ゲートキーを入手するためには、一定の手順に従わなくてはならない。ただ単に対抗チームとの戦闘に勝てばいいってもんじゃないんだ。
一度の戦闘で勝敗が決すると、勝者には、入手したいゲートキーの宝玉を指定するか、相手の所持している宝玉のリストを開示させるか、いずれかの権利が与えられる。指定の場合、指定した宝玉を相手が所持していない場合、請求がキャンセルされ、せっかく勝ってもパーになってしまう。開示の場合、相手からキーを受け取ることはできない。
運に任せて一発入手を狙うか、二度目の戦闘のときに確実にゲットするか。もちろん、一度勝ったからといって、同じ相手にもう一度勝てるとは限らないし、勝ったとしても、相手がよそのチームに該当する宝玉をすでに獲られている可能性もある。
一つの宝玉には複数の魔法効果が備わっていて、それらは他の宝玉が持つ効果と重複している。違うのは組み合わせだ。
攻撃、防御魔法には種類だけでなくレベルの違いもある。高威力の魔法ほど、引き出せる宝玉の種類が少なくなる。例えば、炎属性のヒート・氷属性のコールド・雷属性のエレクトといった攻撃魔法には、単体攻撃のレベルⅠから広範囲攻撃で威力も高いレベルⅢまであり、レベルⅠは七つ、レベルⅡは五つ、レベルⅢは三つの宝玉でしか使えない。最高位魔法ともなれば、対応する宝玉は固有の一つのみだ。
さらに応用編になるが、二つないし三つの宝玉をセットで持っているときのみ使える上級のハイブリッド魔法もある。
強力な魔法を行使すれば戦闘では有利だが、負けた場合には所持している宝玉が何かが相手にバレてしまい、奪われやすくなる。魔法の組み合わせ方についても同様だ。つまり、相当高度な戦略性が要求されるわけだ。一種のカードゲームに近い。
ここでは俺たちが負けてしまったので、コールとオープンのどちらを要求するのか、勝者である【トリアーデ】のホストに尋ねたわけだ。
「フッフーン♪ どうせオープンでくると思ってるでしょぉ。でも、残念でしたぁ。コールで行きまぁす!」
俺は耳を疑った。向こうも俺たちと同じく緒戦であるのは間違いない。こっちの所持する宝玉を当てられる確率は、サイコロの目と同じ六分の一。それにしちゃ、あの自信たっぷりな様子はどうだろう?
と、ひろみはトリピンク=ヒメにゴニョゴニョと耳打ちしてから、両の手を組み合わせてねじり、斜め下からのぞきこむ、小学校のころに流行ったおまじないをやった。ニヤリと笑みを浮かべる。
「じゃあ、いっくよぉー! あたしたちが要求するのはぁ──」
思いっきり深呼吸してから一気に吐き出すように、ひろみは大声で叫んだ。
「ズバリ、シトリンの宝玉でぇーす!」
俺は思わず、胸もとにぶら下げたゲートキーを取り出して宝玉の種類を再確認した。
う、嘘だろ!? いきなり一回目からこっちの手札を当てるなんて……。
ミオもジュディも、いまの戦闘でシトリン固有の魔法は一度も使用していない。そもそも宝玉魔法をほとんど使わなかったし。いまのは完全に当てずっぽうだったはずだ。
ルールに則り、仕方なく要求されたシトリンのゲートキーをひろみに手渡す。いまごろになって、悔しさがこみあげてくる。
「やりぃ!」
「楽勝ッス!」
「リーダー、ナイスですの!」
意気揚々と引き返したひろみは、三人のクライアントにもみくちゃにされた。
チーム【トリアーデ】が、緒戦で白星を収めたうえ、四つめのゲートキーまで手に入れた自らの快挙に沸きあがっている間、俺は自分の不甲斐なさを噛みしめながら、ただ呆然と立ち尽くした。
ミオがいつのまにか隣に来て、俺の目を真剣な眼差しでじっと見つめる。ジュディも。
「さあ、どうすんの、トウヤ? ゲートキーがゼロにニャッた時点で、あたいたちはあんたとサヨニャラよ。あんたは本当にそれでいいの?」
俺はミオとジュディの顔を交互に見やって、きっぱりと首を横に振った。
「そんなのはいやだ! せっかく新しい世界に来たって、お前たちがそばにいてくれないんじゃ意味がない。それじゃ、生き返ったことにならない。俺、お前たちと一緒に戦うよ! もう迷わない。そして、必ず優勝してゲートを開く権利を手に入れてみせる!!」
「そうこなくっちゃ!」
ジュディは両手に持った剣を頭上にかざすようにして、やおら柔軟体操を始めた。まるで、いまのは本番前の軽い準備運動だったと言わんばかりに。さっきまで荒い息をして立つのもやっとに見えたのが嘘のようだ。
ミオも目を細めてゆっくりとうなずいた。
「ちょっと待ちニャさい、そこの短足トリオ! リベンジを要求するわ!」
ミオが【トリアーデ】に向かってビシッと指を突きつける。お座敷列車じみた彼らの船、ゴールデン轟天号に乗り込みかけていた四人は、間の抜けた顔でこちらを振り返った。
「へ? な、何それぇ?」
ひろみが素っ頓狂な声をあげる。
「もう一戦やるのよ。いまこの場で」
「そ、そんなのずるいですぅ! 反則ですぅ! だってだって、ちゃんとあたしたちが勝ったじゃないのよぉ!? やり直しなんてあんまりですぅ!!」
だだっ子のように地団太を踏むひろみに、ミオがうんざりした声で補足説明を加える。
「あんたたち、PIAのルールブックにきちんと目を通してニャイの? まったく、最後までよく聞きニャさい。やり直しじゃニャイわよ。このまま連戦に突入するって言ってるの。魔力の補充もニャシでね。勝負のルールも同じ」
通常は一度戦闘を行い勝敗が決したら、宝玉のダークエネルギーが再び満タンに満たされるまで、次の戦闘を回避できるのがルールだ。ただし、敗者側に限って、補充を待たずに一度対戦した相手チームに再度戦いを挑む権利もある。どう考えても不利なので、行使される機会はまずなさそうが。
【トリアーデ】の四人は、しばらく顔を寄せ集めてコソコソと相談していたが、やがて向き直った。
「ええっとぉ、ほ、ほんとにいいんですかぁ?」
「いいのいいの。遠慮は無用よ」
それを聞いたひろみは、にんまりとして目を輝かせた。
「ムフフフ♥ 一日のうちに二つもゲートキーが手に入るなんて、超ラッキィー♪ これもエメ……じゃなくって、日ごろの行いがいいせいだよねぇ♪ ねぇ、お前たち?」
「リーダーの言うとおりッス」
クライアントの三人は二つ返事でうなずいている。こうして見ていると、幼稚園の年少組に慕われる年長組のお姉さんといった感じだ。
ひろみはどんと胸をたたいてみせた。
「さあ、そんなにもう一度のされたいなら、かかってらっしゃぁい!」
そして、再び二十分後──。
俺の目の前には、さっきとは正反対に、ミオとジュディにこてんぱんにやられてすっかり伸びているタロ、ジロ、ヒメの姿があった。
「もうヘロヘロですのぉ~……」
「そんな……おいらたちさっき勝てたはずなのに……宝玉だって、おいらたちのほうが二つも多いはずなのに……」
「ぐ、悔じいッス……」
ひろみも、まだ目の前の現実を受け入れられないという顔つきで、かぶりを振るばかりだ。
「う、そぉ……どうしてぇ……!?」
へばっている三人とホストを冷たく見下ろしながら、ミオが解説した。
「バカね。あんたたちの戦い方には戦術性のかけらもニャイ。始めっから大技をガンガンぶっ放して手の内をさらしてるようじゃ、底が知れるわ。どのみち、レベルの高い魔法をレベルの低い使用者が使っても効きやしニャイ。あんたたちが宝玉魔法に頼りきって、基礎鍛錬を怠っていた証拠。せっかく最高級のカードを手札にしニャがら台無しね。おまけに、いまあたいたちから獲ったシトリンを、効果を調べることも、戦術の組み立て方を再検討することもしニャイで、いきニャり使おうと試みた。冒険ニャンてもんじゃニャイ。あたいたちだったら、魔法一発打たニャくたって勝てるわ。お遊戯でやってるあんたたちとは本気度が違うのよ」
ジュディも腰に下げたベルトに剣をしまいながら、そのとおりだとうなずく。
「ボクとミオは、トウヤがこっちに来るまでの一年間、モンスター相手に基礎体力と魔力を底上げするトレーニングにみっちり取り組んでたんだからな」
そうだったのか……。
待っていてくれただけでもうれしいけど、ミオとジュディが自分のためにそこまでしてくれていたのかと思うと、胸の内に熱いものがこみあげてきた。決心の定まらない俺に対して二人が憤ったのも当たり前だよな。
ひろみはその場にぺったりとしゃがみこんだ。不意に顔がゆがんだかと思うと、大声をあげて泣きだす。
「う……うう……うわぁああぁあぁぁあぁあん!!」
「リーダー、そんなに泣くなよ。おいらたち、次こそはがんばって勝利をつかむからさ!」
「そうッス。リーダーが泣いてると、あっしらも悲しくなるッス」
「ファイトですの!」
三人のクライアントが、自分たちももらい泣きしながら、肩をたたいたり頭をなでたりして、しきりにホストを慰めている。見ていて心温まる情景だ。
だが、ミオは情け容赦なく片手を突き出した。
「そんニャに悔しかったら、くだらニャイ戦隊ショーごっこニャンかしてニャイで、気合入れて特訓に励むのね。顔を洗って出直してらっしゃい。さ、出すもの出してもらいましょうか」
ひろみはようやく泣きやむと、渋々と応じた。
「シトリンなら返すわよぉ」
「んー、それはいいわ。一通り効果はチェックしたし。あんまり実戦向きじゃニャイからね。そいつを持ってたら財運は上がるけど、当座必要な装備はもう入手済みだから。あんたたちにあげる。その代わり、エメラルドをもらっとくわ」
「ええ~~っ!? ど、どうしてあたしがエメラルドのゲートキーを持ってること、わかったんですかぁ!?」
うろたえるひろみに、ミオが種を明かしてやる。
「あんた、さっきあたいたちの宝玉を言い当てるのに、エメラルドの魔法ラックレベルⅢを使わせたでしょ。残りの二つもバレバレ。当ててみせよっか? オパールとガーネット。図星でしょ?」
「がああ~~ん!」
ひろみは二の句も告げず、ムンクの叫びのポーズをとるばかりだ。
「さっきも言ったけど、あんたたちの戦い方には戦術性ってもんがニャさすぎるわ。このゲームは、頭を使わずに勝てるほど生易しいもんじゃニャイのよ。せいぜいよく研究することね」
彼女からエメラルドのゲートキーを受け取ると、ミオはにんまりと目を細めた。
チーム【トリアーデ】の四人は、肩を寄せ合いながらすごすごと轟天号の中に引き揚げていった。ひろみは最後に一度こちらを振り返って、俺のことをきっとにらみつけた。
「トウヤちゃん、覚えてなさいよぉ! 今度会ったときはギッタギタのフルボッコにしてやるですぅ!!」
たじろぐ俺に向かって捨て台詞を残し、あっかんべえをすると、エアロックに消える。
退場の仕方も、正義の味方というより悪の軍団だったな……。
にぎやかな四人組に似つかわしい騒々しい音と光を振りまきながら、ゴールデン轟天号が発進する。
【トリアーデ】の船が雲の彼方に消えるのを見送ってから、俺は改めて二人のチームメンバーを振り返った。
「二人とも、ありがとな」
そう言って深々と頭を下げる。ミオとジュディが最初わざとやられたふりをしたのは、俺にやる気を出させるための一種のショック療法だったと、もうわかっていたから。
「固いことは言いっこなしだよ」
ジュディは、さっきまでプンプン怒っていたのが嘘のように、ニコニコしながら答えた。それは尻尾を見ても……おっと、尻尾をまじまじと見つめるのはエチケット違反だったな。
ミオもにっこりと微笑むと、たったいま入手した戦利品であるエメラルドのゲートキーを俺の手に握らせ、こう言った。
「エメラルドの石言葉はね、〝新たニャ始まり〟よ」
そっか、それでエメラルドを……。もちろん、実用性も当然考えてのことだろうけど。エメラルドは、エレクトのレベルⅢを始めとする強力な攻撃魔法も備えており、アニマストーンの中でもとくに価値の高い一級品だ。
「その代わり、特訓にはしっかりつきあってもらうからね! 魔法が使えなくたって、剣の受身くらいできるだろ?」
「いい、トウヤ? あんたの役割は、自分が想像している以上に重要ニャのよ。今回は相手がアレでラッキーだったけど、次からはこうはいかニャイ。あたいたちは実戦では余裕がニャイから、相手方の宝玉の種類を見極めるのはあんたの役目。二十一の宝玉の性質と魔法の組み合わせについて、しっかり頭にたたきこんでもらうわよ」
こうして俺は、仲直りしたのも束の間、ジュディからは「根性なし!」と、ミオからは「バカ」と言われ続ける、さんざんな日々を送ることになった──
十日後、俺たちは惑星ミリアⅣでチーム【トリアーデ】とたまたま遭遇。再び勝利を収め、今度はガーネットのゲートキーをゲットした。主題歌と登場シーンの演出にはさらに磨きがかかっていたが、それ以外は進歩がなかった。
ひろみはこのときも、「次に会ったときこそ覚えてなさいよぉ!」と同じ捨て台詞を残し、すごすごと退却した。


